建設業会計の特殊勘定科目とは?業務効率化や資金調達までのポイントも徹底解説

建設業界は他業種とは異なる独自の商習慣と会計処理を有しています。
工事ごとに異なる現場の管理、長期にわたるプロジェクト、下請けとの複雑な取引関係など、建設業特有の課題が会計処理にも大きな影響を与えています。
しかし、多くの中小建設業の経営者は、この特殊性を十分に理解せずに会計処理を行っているケースが少なくありません。
適切な会計処理は単なる法令遵守の問題ではなく、正確な経営判断、有利な資金調達、そして将来のM&A時の企業価値評価に直結します。
株式会社デルタではDX化に役立つシステム開発や運営、資金調達のコンサルティングも行っております。
本記事では、建設業特有の勘定科目の基礎から、電子帳簿保存法への対応、そしてDXを活用した会計業務の効率化まで、経営者として押さえておくべきポイントを解説します。
建設業会計の基礎知識

建設業の会計は複雑で独特の処理が求められるため、多くの経営者が頭を悩ませています。
通常の事業会社とは異なる収益認識の方法や工事台帳の管理など、建設業ならではの会計上の課題が山積しています。
これらを正しく理解し適切に対応することが、健全な経営と成長のための第一歩となります。
一般企業との会計処理の違い
建設業の会計処理は、一般の製造業やサービス業とは大きく異なります。
主な特徴として、工事の進行に応じて収益を認識する「工事進行基準」と、工事完成時に一括して収益を認識する「工事完成基準」の選択があります。
中小建設業では工事完成基準を採用するケースが多いものの、正確な経営状況を把握するためには工事進行基準の考え方も理解しておく必要があります。
また、建設業は「建設業法」に基づく規制があり、公共工事の入札参加資格審査や経営事項審査(経審)においては、財務諸表の内容が直接評価の対象となります。
そのため、適切な会計処理は単なるコンプライアンスの問題ではなく、事業機会の確保にも直結するのです。
建設業の事業年度は3月決算が多いものの、工事の完成時期に合わせて9月や12月決算を選択する企業も少なくありません。
決算月の選択も戦略的に検討すべき重要な要素といえるでしょう。
建設業会計の特殊な勘定科目

建設業の財務諸表には一般企業では見られない特殊な勘定科目が数多く存在します。
これらの科目は単なる名称の違いではなく、建設業の事業構造や収益認識の特殊性を反映したものです。
正確な経営状態を把握し、適切な意思決定を行うためには、これらの勘定科目の本質と相互関係を理解することが不可欠です。
完成工事高・完成工事原価
建設業では売上を「完成工事高」、売上原価を「完成工事原価」と呼びます。
これらは一般企業の「売上高」や「売上原価」に相当しますが、工事ごとの収支管理が必要なため、工事台帳との連動が重要です。
「完成工事原価」には材料費、労務費、外注費、経費などが含まれますが、工事に直接関連しない本社経費などは「販売費及び一般管理費」として区分します。
この区分が曖昧になると、工事別の採算性が不明確になり、見積精度の低下や赤字工事の見落としにつながる恐れがあります。
未成工事支出金・未成工事受入金
進行中の工事に関わる支出は「未成工事支出金」として資産計上します。
これは一般企業の「仕掛品」に相当するものです。
一方、工事の着手金や中間金として受け取った前受金は「未成工事受入金」として負債に計上します。
特に「未成工事支出金」は建設業の貸借対照表において重要な位置を占めており、長期にわたる工事では金額も大きくなります。
そのため、定期的な実態調査と評価が必要です。不適切な計上は粉飾決算と見なされるリスクもあります。
工事損失引当金
受注済みの工事のうち、将来の損失発生が見込まれるものについては「工事損失引当金」を計上する必要があります。
これは工事進行基準、工事完成基準のどちらを採用している場合でも計上が必要で、健全な財務状態を示すために重要です。
しかし、中小建設業では損失見込みの工事があっても引当金を計上していないケースが多く見られます。
これは短期的には利益を多く見せることができますが、長期的には突然の損失計上につながり、金融機関からの信用低下を招く恐れがあります。
共同企業体(JV)関連の勘定科目
大型工事では複数の建設会社が共同企業体(Joint Venture:JV)を組成して受注するケースがあります。
JVに関連する取引は「JV工事未収入金」「JV工事未払金」などの科目で処理します。
JV工事の会計処理は複雑なため、幹事会社との連携を密にし、正確な処理を心がける必要があります。
特にJVの持分比率に応じた収益・費用の計上は、自社の財務状況を正確に反映させるために重要です。
電子帳簿保存法への対応
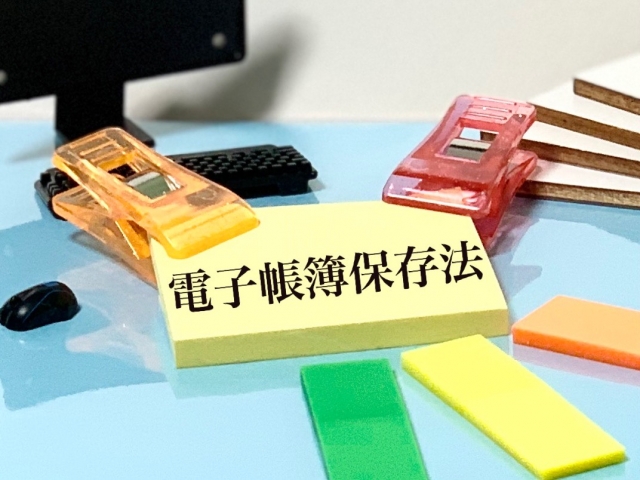
電子帳簿保存法の改正は建設業界にとって特に大きな変化をもたらしています。
紙ベースの書類管理が主流だった建設現場においては、この法改正への対応は単なるコンプライアンス対応ではなく、業務プロセス全体の見直しを迫るものです。
しかし、この変化を前向きに捉え、DX推進の好機と位置づけることで、競争力強化につなげることができます。
電子保存の義務化とスケジュール
2022年1月から段階的に施行されている電子帳簿保存法の改正により、2024年1月以降は、一定の要件を満たす事業者に対して電子取引データの電子保存が義務化されています。
建設業においても、取引先とのメールやPDFでのやり取り、クラウドシステムでの請求書受領などは電子取引に該当し、保存義務の対象となります。
建設業特有の書類とその取り扱い
建設業では、見積書、契約書、請求書といった一般的な書類に加え、工事指示書、施工計画書、工程表、検査調書、出来高報告書など多種多様な書類が発生します。
これらすべてを適切に管理・保存するためには、体系的な文書管理システムの導入が不可欠です。
違反した場合のリスク
電子帳簿保存法に違反した場合、最悪のケースでは青色申告の承認取消しや重加算税の適用などのペナルティを受ける可能性があります。
また、税務調査の際に取引の正当性を証明できないと、経費として認められないリスクもあります。
対応のための最低限必要なステップ
- 電子取引の洗い出しと分類
- 適切な保存方法の選定(タイムスタンプ付与、検索機能の確保)
- 社内規程の整備と従業員教育
- 定期的な運用状況の確認
国税庁が公表している「電子帳簿保存法一問一答」を参照しながら、自社の状況に合わせた対応を進めることをお勧めします。
建設業DXによる会計業務の効率化

建設業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なる業務のデジタル化を超えた経営革新をもたらします。
特に会計業務のDXは、正確性向上、効率化、リアルタイム性確保という三つの大きなメリットをもたらします。
これにより経営者は迅速かつ正確な意思決定が可能となり、競争が激化する建設市場での優位性を確保できるのです。
現場と会計の連携によるリアルタイム管理
建設業における最大の課題の一つは、現場と事務所(会計)の情報連携の遅れです。
タブレットやスマートフォンを活用した現場報告システムを導入することで、日々の作業報告、材料の使用状況、労務管理などをリアルタイムで把握できるようになります。
これにより、未成工事支出金の正確な把握や、工事損失の早期発見が可能となり、経営判断の質が向上します。
また、月次決算の早期化も実現でき、資金繰り管理の精度向上にもつながります。
クラウド会計と建設業向けシステムの連携
建設業向けの工事管理システムとクラウド会計ソフトを連携させることで、二重入力の削減と記帳ミスの防止が可能になります。
多くのシステムではAPI連携が進んでおり、工事台帳の情報が自動的に会計データに反映される仕組みが整いつつあります。
特に、工事別の原価管理と一般会計を連動させることで、プロジェクトごとの採算性をリアルタイムで把握できるようになります。
これは見積精度の向上や適正な受注判断に直結する重要な情報となります。
工事台帳のデジタル化によるメリット
工事台帳は建設業会計の基礎となる重要書類です。これをデジタル化することで、以下のようなメリットが生まれます:
- 工事別の収支状況をリアルタイムで把握
- 過去の類似工事とのコスト比較が容易に
- 予実管理の精度向上
- 電子帳簿保存法への対応が容易に
紙ベースの工事台帳からデジタル管理への移行は、単なる効率化だけでなく、戦略的な経営判断を支える基盤となります。
適切な会計処理がもたらす資金調達への好影響

建設業が持続的に成長するためには、適切なタイミングでの資金調達と、将来的な事業承継やM&Aを視野に入れた経営が重要です。
適切な会計処理は単なる数字合わせではなく、企業の実態を正確に映し出す「経営の鏡」としての役割を持ちます。
この鏡が曇っていては、金融機関や投資家、M&A相手企業からの適正な評価を得ることはできません。
金融機関の評価ポイント
金融機関は建設業への融資審査において、一般的な財務分析に加え、以下のような建設業特有の指標に注目しています:
- 完成工事高総利益率(粗利率)
- 未成工事支出金回転率
- 工事別の採算性
- 工事債権の回収状況
適切な会計処理によって、これらの指標を正確かつ好ましい形で示すことができれば、融資条件の改善や借入枠の拡大につながります。
財務諸表の健全性と融資条件の関係
建設業は他業種に比べて運転資金需要が大きく、資金調達力が経営の安定に直結します。
特に公共工事では入金までの期間が長いため、適切な資金計画が不可欠です。
財務諸表が適切に作成され、特殊な勘定科目の処理が正確であれば、金融機関からの信頼獲得につながります。
これは金利の引き下げや無担保融資枠の拡大など、具体的なメリットをもたらします。
M&A時の企業価値評価における会計処理の重要性
建設業界では後継者不足を背景に、M&Aによる事業承継が増加しています。
企業価値評価の際には、過去3〜5年の財務諸表が詳細に分析されます。
この際、建設業特有の勘定科目の処理が適切でないと、企業価値が適正に評価されないリスクがあります。
特に未成工事支出金の評価や工事損失引当金の計上状況は、デューデリジェンスのプロセスで必ず精査される項目です。
M&Aを視野に入れている経営者は、普段から適切な会計処理を心がけることが重要です。
まとめ:建設業会計の特殊な勘定項目へ適切な対応を
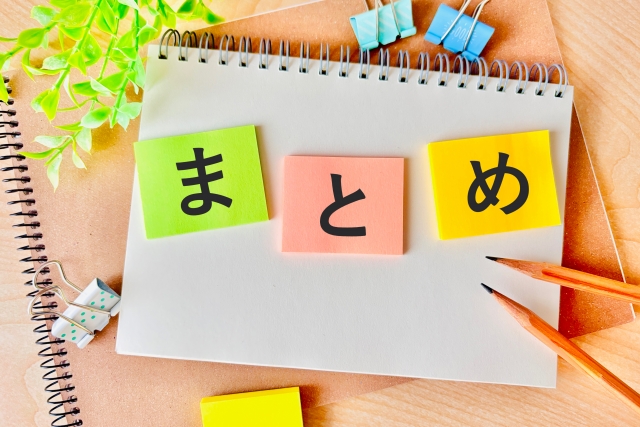
建設業特有の勘定科目を正しく理解し、適切に処理することは、単なる法令遵守を超えた経営戦略の一環です。
電子帳簿保存法への対応とDX推進を組み合わせることで、会計業務の効率化だけでなく、経営判断の質向上、有利な資金調達、そして企業価値の最大化を実現できます。
株式会社デルタではDX化に役立つシステム開発や運営、資金調達のコンサルティングも行っております。
貴社の現状や課題に合わせた最適な会計DX戦略については、ぜひ個別にご相談ください。
建設業特有の会計課題から資金調達、M&Aまで、経営全般をサポートする専門家が対応いたします。
