建設業の経理担当が一気に楽になる!インボイス制度対応の領収書の書き方とは?記載例つきでわかりやすく解説

2023年10月から始まったインボイス制度によって、これまでの領収書の書き方も変わってきました。
特に建設業では、下請けや資材購入など様々な取引があるため、制度への対応が複雑に感じられるかもしれません。
株式会社デルタでは建設業に特化したシステム開発も行っております。
インボイスにも対応したDX化をお考えの方はぜひお問い合わせください。
この記事では、建設業の方々が知っておくべきインボイス制度に対応した領収書の書き方について分かりやすく解説します。
インボイス制度とは?

インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除の方式が変わる制度です。
この制度により、取引先から受け取る請求書や領収書には、一定の記載事項が必要となりました。
特に建設業は一人親方や下請業者との取引が多いのが特徴です。国税庁によると、建設業はBtoB事業が多く、免税事業者であることが多い一人親方が発注先の大きな比率を占めています。
そのため、インボイス制度の影響は他業種よりも大きいと言えるでしょう。
[インボイス制度の概要]
- 登録事業者しか発行できない
インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録した事業者のみ - 必要な記載事項が増えた
従来よりも記載項目が増加し、特に「登録番号」と「税率ごとの消費税額」の記載が重要 - 建設業者への影響
下請業者がインボイス発行事業者でないと、元請業者は仕入税額控除を受けられない
建設業では材料費や外注費など、多くの経費に関わるため影響が特に大きいと言えるでしょう。
例えば、年間1,000万円の外注費を免税事業者に支払っている場合、100万円の消費税が控除できなくなる可能性があります。
建設業のインボイス対応領収書に必要な記載事項
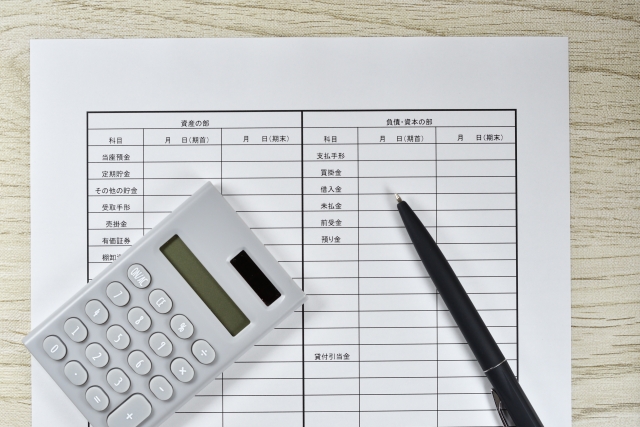
インボイス制度に対応した領収書(適格請求書)には、以下の項目を必ず記載する必要があります。
| 必須記載事項 | 説明 | 記載例 |
| 発行者の氏名・名称 | 建設会社の正式名称 | 山田建設株式会社 |
| 登録番号 | T+法人番号(13桁) | T1234567890123 |
| 取引年月日 | 工事日または受取日 | 2025年5月4日 |
| 取引内容 | 工事名や内容を具体的に | 〇〇邸新築工事 |
| 税率と合計額 | 税率区分と金額 | 450,000円(10%) |
| 消費税額 | 各税率の消費税額 | 消費税:45,000円 |
| 受領者名称 | 発注者名または会社名 | 株式会社大阪不動産 |
建設業におけるインボイス対応領収書の具体的な書き方と記載例

単一税率が発生する場合の記載例
【領収書(適格請求書)】
発行者:山田建設株式会社
登録番号:T1234567890123
取引日:2025年5月4日
宛先:株式会社大阪不動産
内容:大阪市中央区〇〇ビル外壁補修工事
【内訳】
10%対象:450,000円
消費税(10%):45,000円
8%対象:0円
消費税(8%):0円
合計金額:495,000円
上記金額を正に領収いたしました。
複数税率が発生する場合の記載例
建設業では、標準税率(10%)と軽減税率(8%)が適用される場合が一般的です。
【領収書(適格請求書)】
発行者:山田建設株式会社
登録番号:T1234567890123
取引日:2025年5月4日
宛先:大阪総合病院
内容:病院内装改修工事および自動販売機設置
【内訳】
工事代金:500,000円(税率10%)
消費税(10%):50,000円
飲料自販機商品初期在庫:30,000円(税率8%)
消費税(8%):2,400円
合計金額:582,400円
上記金額を正に領収いたしました。
一式表記・人工費を使用する場合の記載例
建設業では「〇〇工事一式」という記載や、「人工費」という表現がよく使われます。
インボイス制度においても、これらの表記は可能ですが、記載方法に注意が必要です。
【領収書(適格請求書)】
発行者:山田建設株式会社
登録番号:T1234567890123
取引日:2025年5月4日
宛先:株式会社大阪不動産
【内訳】
〇〇邸外壁塗装工事一式:400,000円(税率10%)
消費税(10%):40,000円
合計金額:440,000円
上記金額を正に領収いたしました。
または人工費を使用する場合:
【内訳】
大工作業 2人工:60,000円(税率10%)
左官作業 1人工:30,000円(税率10%)
消費税(10%):9,000円
合計金額:99,000円
上記金額を正に領収いたしました。
注意すべきポイント
注意すべき重要事項
- 区分記載:税率の異なる取引は必ず区分して記載してください
- 具体的記載:「工事一式」ではなく、具体的な工事名や場所を記載しましょう
- 社印や署名:インボイス制度では必須ではありませんが、信頼性を高めるために付けることをお勧めします
- 端数処理:インボイス制度では「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回のみ端数処理を行う」というルールがあります
- 少額取引:3万円未満の取引でも、インボイス制度導入後は領収書が必要です(一部例外あり)
- 保存期間:領収書の保管期間は7年間です。紛失すると税務調査で追徴課税のリスクがあります
建設業特有のインボイス対応のポイントとよくある疑問

下請業者との取引
建設業では下請業者との取引が多いため、インボイス制度への対応が特に重要です。
| 対応策 | メリット | デメリット |
| 下請業者に登録を依頼 | 取引関係を維持できる | 相手が応じない可能性 |
| 登録業者への変更 | 確実に税額控除可能 | 新規取引先開拓コスト |
| 経過措置の活用 | 一定期間は部分控除可能 | 年々控除率が下がる |
経過措置では、2023年〜2026年は80%、2026年〜2029年は50%の仕入税額控除が認められています。
一部のみ完了した工事の請求
長期工事の部分完成時の対応も、インボイスの要件を満たす必要があります。
「〇〇工事 第一期分」など、取引内容を明確に記載しましょう。
手書きの領収書でも可能か?
インボイスは手書きでも有効です。
ただし、必要事項をすべて記載する必要があります。
記載漏れがないよう、テンプレートを作成しておくと便利です。
消費税の端数処理
消費税計算の端数処理は、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれも認められています。
ただし、一度選択した方法は継続適用が原則です。
インボイス対応領収書のおすすめ管理方法

建設業は多くの取引先や現場を抱えているため、効率的な管理が特に重要です。
建設業における書類の保存方法について
- 領収書の保存形式
紙の領収書は紙のまま、電子で受け取った場合は電子データのまま保管する必要があります - 適格請求書の控え保存義務
適格請求書を発行した場合は、その写し(控え)の保管も法律で義務付けられています - 書類整理の方法
建設業では現場ごとの管理が必要なため、プロジェクトコードなどで整理することをお勧めします
おすすめの管理ツール
- 会計ソフト
freee、MFクラウドなどは自動で必要事項を記載し、現場ごとの収支管理も可能です - 請求書アプリの使用
スマホで発行可能で、現場での即時発行に役立ちます - 自作テンプレートシート
エクセルやワードで自社用のテンプレートを作成しておくと便利です
電子帳簿保存法への対応
領収書や請求書を電子データで保存することで、保管スペースの削減、検索性の向上、災害対策といったメリットがあります。
建設業では多数の工事関連書類を保管する必要があるため、特に大きなメリットを得られるでしょう。
取引先管理の徹底
建設業では多くの協力業者や下請け業者と取引をすることが一般的です。
これらの取引先がインボイス発行事業者かどうかを把握することで仕分けが楽になります。
効率的な取引先管理方法
- エクセルなどで取引先リストを作成し、登録番号や登録状況の記録
- 定期的に国税庁の「インボイス発行事業者公表サイト」で確認
- 新規取引を開始する際は、事前に相手がインボイス発行事業者かどうかを確認する
特に建設業では、工事ごとに異なる業者と取引することもあるため、取引先管理が煩雑になりがちですが、きちんと管理しておくことで後々のトラブルを防ぐことができます。
また、取引先にインボイス登録を促すことも、自社の税負担を適正に保つために重要な対策となります。
まとめ

建設業のインボイス対応チェックリスト
- ✓ 適格請求書発行事業者の登録を完了している
- ✓ 領収書に「登録番号」を記載している
- ✓ 税率ごとの消費税額を明記している
- ✓ 取引内容を具体的に記載している
- ✓ 下請業者のインボイス登録状況を確認している
インボイス制度に適切に対応することで、取引先との信頼関係を維持し、税負担を適正に保つことができます。
さらに、大手ゼネコンなど、インボイス対応を取引条件とする発注者も増えていますので、早めの対応が事業の拡大につながります。
株式会社デルタでは建設業に特化したシステム開発も行っております。
インボイスにも対応したDX化をお考えの方はぜひお問い合わせください。
