建設業の公共工事はどう変わる?インボイス制度の影響と対応策まとめ【2025年最新】

2023年10月よりスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、建設業界に大きな影響を与えています。
特に公共工事を手がける中小建設業にとって、この制度変更への対応は避けて通れない課題となっています。
本記事では、インボイス制度の基本から建設業・公共工事への影響、そして具体的な対応策までを分かりやすく解説します。
株式会社デルタでは建設業に特化したシステムの開発や運営も行っております。
現状でお使いの会計ソフトでの会計処理に不安を感じているなどあれば、ぜひ株式会社デルタにお問い合わせください。
インボイス制度とは?基本のおさらい
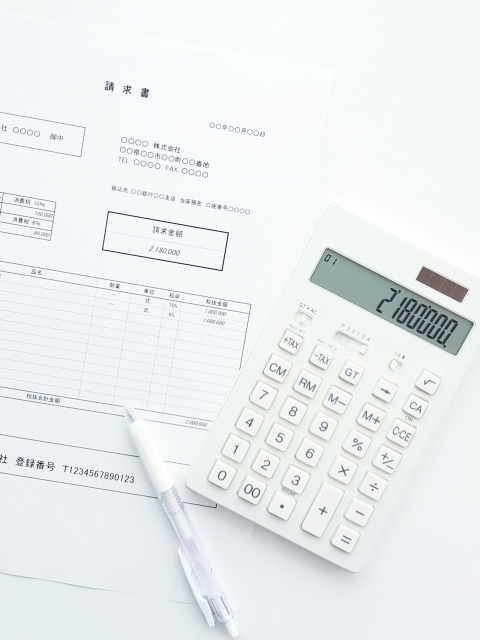
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、2023年10月から導入された消費税の仕入税額控除の仕組みです。
適用税率や消費税額などが記載された適格請求書を交付・保存する制度で、課税事業者はこの適格請求書を取引の際に交付し、保存する必要があります。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
適格請求書には以下の項目を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き・税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
こうした記載事項を満たした請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録を受けた課税事業者のみです。
消費税の課税事業者(年間売上1,000万円超)は、インボイスの発行事業者になるために税務署での登録手続きが必要です。
一方、売上1,000万円以下の免税事業者がインボイスの発行事業者になるには、課税事業者の登録手続きが先に必要となります。
仕入税額控除の仕組み
インボイス制度導入により、課税事業者は仕入れにかかった消費税の控除を受けるために、仕入れ先から適格請求書を発行してもらう必要があります。
適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除ができなくなりました。
しかし、実際には取引継続を優先して免税事業者でも課税転換・適格請求書発行事業者への登録を進める動きが加速しています。
国税庁の最新データでは、2025年1月時点で建設業の一人親方を含む免税事業者の約7割がすでに登録済みとされており「免税ゆえに控除できない」というケースは着実に減少中です。
建設業界への影響

インボイス制度は、建設業界の商習慣や取引構造に直結する制度変更であるため、他業種以上に影響が大きくなります。
とくに元請けと下請けの関係性、そして免税事業者の多さが制度対応の難易度を上げています。
ここでは、建設業界特有の事情に照らして、制度がどのような影響を及ぼすのかを具体的に見ていきます。
元請け・下請け関係への影響
建設業では一人親方などの免税事業者が多く、インボイス制度導入により元請け・下請けの関係に大きな変化が生じています。
| 影響を受ける側 | 主な影響内容 | 具体的な変化 |
| 元請け建設会社 | 仕入税額控除の制限 | 免税事業者である下請けからの仕入れに関する税額控除が段階的に減少 |
| 元請け建設会社 | 事務負担の増加 | 適格請求書と従来の請求書を区別した処理フローの構築が必要 |
| 下請け(免税事業者) | 取引機会の減少リスク | 適格請求書を発行できないため、取引先から敬遠される可能性 |
| 下請け(免税事業者) | 価格交渉の不利 | 消費税分の値引きを要求される可能性 |
インボイス制度が建設業に与える影響が特に大きい理由は、建設業ではBtoB事業が多く含まれており、一人親方が発注先として大きな比率を占めているためです。
建設業者がインボイスを発行しない免税事業者から材料や労務の提供を受けた場合、その仕入れにかかる消費税は控除の対象とならずコスト増となります。
このため、元請け業者は免税事業者との取引を避ける傾向が生まれ、免税事業者である下請けは厳しい選択を迫られています。
公共工事における変化

公共工事は元請けベースで7,000万円規模からですが、下請・専門工事への再下請や自治体の小規模修繕(450〜800万円以下)も存在します。
そのため、公共工事に関与していても 年間課税売上高1,000 万円以下の免税事業者も僅かながら残っています。
公共工事は法的・制度的なルールが厳格であるため、インボイス制度の影響も顕著に現れています。
特に入札や契約に関する要件の変更が、実務面での負担増加につながっています。これまでのやり方を続けていると対応が遅れ、結果的に事業機会を逃すリスクが高まります。
入札・契約段階での影響
公共工事の入札・契約段階においては、下請け構成の精査がより厳格になりました。
元請けは各下請けに対し、まず「適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)」の提出を求め、その有無でインボイス発行可否を判定します。
- 登録番号がある場合
見積書や契約書に登録番号を明記し、消費税を課税仕入れとして計上。 - 登録番号がない(免税事業者)の場合
見積書に「消費税は請求しない」「控除不可分○円を値引き」などを明示させ、控除対象外コストを区分。
こうした手順により、見積り段階から消費税関連コストを正確に算定し、免税事業者を含む場合は控除不可分の増加コストを入札価格に反映するか、負担者を契約上で明確化する必要があります。
公共発注者側の対応
国や地方自治体など公共発注者側も、インボイス制度に対応するためさまざまな取り組みを進めています。
一部の自治体では、適格請求書発行事業者であることを入札参加要件に加える動きも見られます。
また、元請け企業への指導強化も行われており、下請け事業者へのインボイス制度対応を促進するよう働きかけが強まっています。
公共工事の透明性確保の観点からも、サプライチェーン全体でのインボイス対応が求められています。
インボイス制度の経過措置と2025年の状況
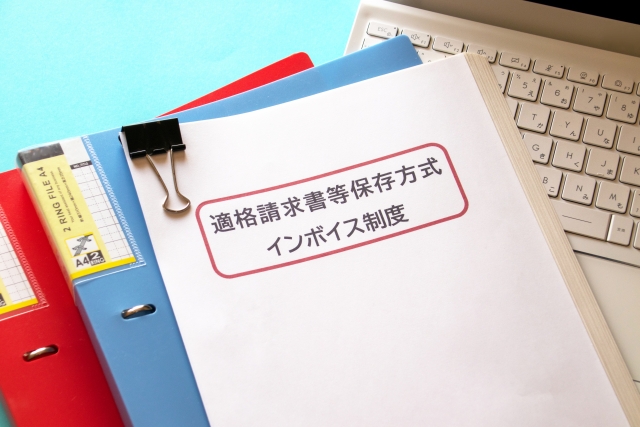
インボイス制度は段階的に導入されており、完全施行までには時間があります。
| 期間 | 経過措置の内容 | 免税事業者の仕入税額控除 |
| 2023年10月〜2026年9月 | 第1期経過措置 | 80%控除可能 |
| 2026年10月〜2029年9月 | 第2期経過措置 | 50%控除可能 |
| 2029年10月以降 | 完全施行 | 控除不可(0%) |
2025年現在は第1期経過措置期間中であり、免税事業者からの仕入れについても80%の仕入税額控除が可能です。
しかし、2026年10月からは控除率が50%に引き下げられるため、今のうちから対応を進めることが重要です。
建設業者のための対応策

インボイス制度への対応は、元請け・下請けの立場にかかわらず不可避な課題です。
制度を正しく理解し、自社に合った対策を講じることで、将来のリスクを最小限に抑えることができます。こ
こでは、それぞれの立場に応じた具体的な対応策を紹介します。
元請け建設会社の対応策
元請け建設会社にとって重要なのは、下請け構成の総点検です。
免税事業者である下請けを特定し、影響額を試算しましょう。
また、発注・契約プロセスの見直しや経理システムの整備も必要です。
具体的な対応策としては、免税事業者である下請けに対して適格請求書発行事業者登録を促すことが考えられます。しかし、これには法的な注意点もあります。
下請法では、免税事業者であることを理由に消費税相当額の支払いを拒むことは禁止されており、下請事業者に対して一方的な不利益を与えるような要求はできないので常に適正な取引関係を維持することが重要です。
発注時の確認プロセスの見直しも必要で、見積り段階から適格請求書発行事業者かどうかを確認する手順を導入しましょう。
契約書式にインボイス関連の条項を追加することも検討すべきです。
下請け・一人親方の対応策
下請けや一人親方は、課税事業者になるか免税事業者のままでいるかを自社の状況に合わせて判断する必要があります。
| 選択肢 | メリット | デメリット | 推奨される業者タイプ |
| 課税事業者になる | 元請けからの取引継続・拡大が期待できる | 消費税納税義務の発生、事務負担の増加 | 安定した取引先を持つ業者
成長志向の業者 |
| 免税事業者のまま | 消費税納税義務なし、事務負担少ない | 取引機会の減少リスク、価格交渉で不利 | 個人客中心の業者
利益率の低い業者 |
課税事業者を選択する場合は、消費税の納税義務が生じるため、キャッシュフローの管理がより重要になります。
また、適格請求書の発行・保存など事務作業も増えるため、効率的な業務体制の構築も必要です。
経理ソフトの導入や税理士への相談など、専門的なサポートを受けることも検討しましょう。
支援措置の活用

インボイス対応を進めるにあたり、各種支援制度の活用も検討しましょう。
IT導入補助金インボイス枠では、システム導入費用の一部が補助されます。
税務署や商工会議所の相談窓口、建設業団体による講習会なども積極的に活用することをおすすめします。
まとめ

インボイス制度は建設業界、特に公共工事に携わる事業者にとって大きな変革をもたらしています。
2025年現在は経過措置期間中ですが、将来的には免税事業者との取引に関する仕入税額控除は完全になくなります。
株式会社デルタでは建設業に特化したシステムの開発や運営も行っております。
現状でお使いの会計ソフトでの会計処理に不安を感じているなどあれば、ぜひ株式会社デルタにお問い合わせください。
