【2025年最新】帳簿書類の保存期間完全ガイド!インボイス制度と電子帳簿保存法の対応策

中小企業の経営において、帳簿書類の適切な管理は単なる義務ではなく、健全な経営の基盤となるものです。
帳簿書類は税務申告の根拠資料であるだけでなく、経営分析や意思決定の重要な情報源となります。
また、金融機関や取引先からの信頼を得るためにも、正確な帳簿管理は不可欠です。
特に近年、インボイス制度の本格導入や電子帳簿保存法の改正により、帳簿書類の保存に関するルールは大きく変化しています。
これらの変更に対応できていない場合、税務調査での指摘や加算税などのペナルティが課される可能性もあります。
株式会社デルタではDX化に役立つシステム開発や運営も行っております。
本記事では、2025年時点での最新情報をもとに、帳簿書類の保存期間のルールと、中小企業が今すぐ取り組むべき対応策について解説します。
帳簿書類の保存期間の基本は7年

帳簿書類の保存期間は、基本的に法人税法および所得税法によって定められています。
中小企業の経営者が最初に覚えておくべきポイントは、ほとんどの帳簿書類は7年間保存する必要があるということです。
この7年という期間は、税務調査の除斥期間に合わせて設定されており、法令遵守の基本となります。
一般的な保存期間は7年間ですが、書類の種類によって異なる場合があります。
会計帳簿の保存期間
- 仕訳帳、総勘定元帳などの主要簿:7年
- 現金出納帳、売掛金元帳などの補助簿:7年
証憑書類の保存期間
- 請求書、領収書、契約書などの取引関係書類:7年
- 給与台帳や源泉徴収関係書類:7年
決算関係書類の保存期間
- 貸借対照表、損益計算書などの決算書:7年
- 棚卸表、減価償却資産台帳:7年
ただし、一部例外もあります。例えば、不動産関連の書類は取得から保有期間中、そして売却後7年間の保存が必要です。
また、消費税の還付申告を行う場合は、その申告に関する書類を7年間保存しなければなりません。
保存期間の起算点は、原則として「事業年度終了の日の翌日から」です。
例えば、3月決算の会社の場合、2024年3月期の帳簿書類は2024年4月1日から2031年3月31日まで保存する必要があります。
帳簿書類の保存期間:インボイス制度の影響

2023年10月に本格導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、帳簿書類の保存に大きな影響を与えています。
この制度は消費税の仕入税額控除の方式を根本から変更するものであり、すべての事業者に関わる重要な制度改正です。
特に中小企業にとっては、適格請求書の発行・受領・保存という新たな業務が発生しており、経理体制の見直しが必要となっています。
インボイス制度への対応状況は、取引先との関係にも影響を与える可能性があるため、適切な対応が求められています。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための制度です。
この制度により、売手は「適格請求書発行事業者」として登録し、「適格請求書(インボイス)」を発行する必要があります。
適格請求書等の保存期間
- 適格請求書(インボイス):7年間
- 適格返還請求書:7年間
特に注意すべき点として、インボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必須となりました。
これにより、従来以上に厳格な書類管理が求められています。
登録事業者と免税事業者の対応
- 登録事業者:適格請求書の発行義務と保存義務の両方があります
- 免税事業者:適格請求書を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります
2025年現在、制度の経過措置期間も進行中であり、2026年10月以降は経過措置による仕入税額控除の割合が段階的に縮小します。
中小企業は早急に対応を進める必要があります。
電子帳簿保存法の改正ポイント
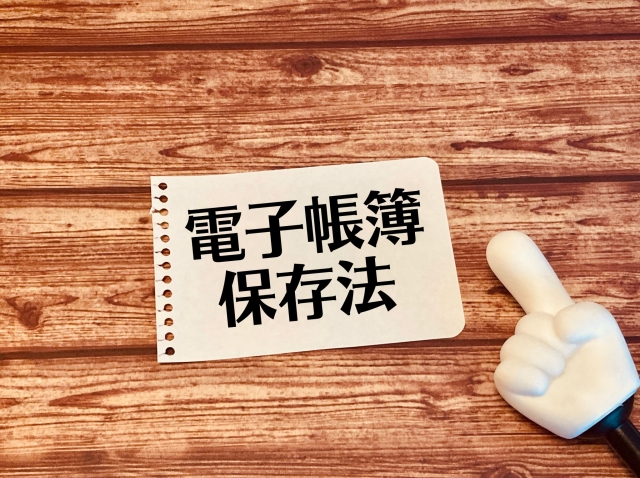
電子帳簿保存法の改正により、2022年から「電子取引データの電子保存」が原則義務化されました。
この改正は、帳簿書類の保存方法に大きな変革をもたらしています。
デジタル化が進む現代社会において、紙ベースの保存から電子保存への移行は避けられない流れとなっています。
多くの中小企業では、メールやクラウドサービスを通じた電子取引が日常的に行われており、これらのデータを適切に保存することが法的に求められるようになりました。
電子帳簿保存法への対応は、単なる法令遵守にとどまらず、業務効率化やペーパーレス化といった経営課題の解決にもつながる重要な取り組みです。
電子取引データの保存義務化
電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引を指します。
具体的には以下が含まれます:
- メールに添付されたPDF請求書
- クラウドサービスからダウンロードする請求書
- EDI取引
- インターネットバンキングのデータ
これらのデータは、7年間の電子保存が義務となっています。
紙に印刷して保存するだけでは、法的要件を満たしません。
猶予期間の終了と最新状況
当初2年間の猶予期間が設けられ、その後延長されましたが、2024年1月以降は完全に義務化されています。
2025年現在、この義務に対応していない企業は早急な対応が求められます。
電子保存のメリット
- 保管スペースの削減
- 検索機能による業務効率化
- テレワーク環境での書類確認が容易
- 災害時のバックアップ体制の強化
未対応のリスク
- 青色申告の承認取消しの可能性
- 重加算税等のペナルティ
- 税務調査での否認リスク
特に、電子取引データを印刷して紙で保存しているだけの場合、その経費が認められないリスクがあります。
帳簿書類を適切に保存するための実践的対応策

帳簿書類の保存期間と方法を理解したら、次は具体的な対応策を検討する必要があります。
中小企業にとっては、限られた人員とリソースの中で効率的に対応することが課題となります。
幸いなことに、テクノロジーの進化により、比較的低コストで導入できるソリューションが増えています。
電子保存のハードルは以前に比べて大幅に下がっており、自社の規模や業態に合わせた最適な方法を選択することが可能です。
以下では、中小企業が実践しやすい具体的な対応策を紹介します。
クラウド会計・経費精算システムの活用
最も効率的な対応策は、クラウド会計ソフトや経費精算システムの導入です。
これらのシステムは、電子帳簿保存法に対応した機能を備えており、以下のメリットがあります:
- 自動的なデータバックアップ
- タイムスタンプ付与機能
- 検索機能の実装
- インボイス制度対応の機能
中小企業向けのクラウド会計ソフトには多数の選択肢があり、月額数千円から利用可能です。
スキャンと原本破棄の要件
紙の書類をスキャンして電子保存し、原本を破棄する場合は以下の要件を満たす必要があります:
- 解像度:200dpi以上
- カラーでのスキャン(カラー書類の場合)
- タイムスタンプの付与
- 検索機能の確保
- 改ざん防止措置
タイムスタンプと検索機能の要件
電子保存においては、以下の点が重要です:
- タイムスタンプ:データの作成時刻を証明する電子的な証明
- 検索機能:取引年月日、取引金額、取引先で検索できること
中小企業におけるコスト効率の良い導入方法
- 段階的な導入:まずは請求書・領収書など頻度の高いものから
- 既存システムの活用:現在利用中の会計ソフトの電子保存機能を確認
- クラウドストレージの活用:専用ソフトがなくても対応可能な方法も
まとめ
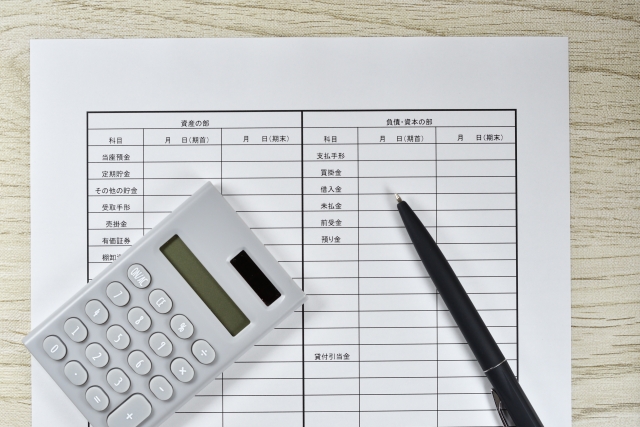
帳簿書類の保存期間は原則7年であり、この基本ルールを守ることがコンプライアンスの第一歩です。
しかし、2025年現在ではインボイス制度と電子帳簿保存法への対応も同時に求められています。
まずは自社の現状を正確に把握することから始めましょう。
電子取引データを適切に電子保存しているか、保存システムが検索機能を備えているか、タイムスタンプが適切に付与されているか、インボイス制度における適格請求書の保存体制は整っているか、そしてバックアップ体制は万全かを確認することが重要です。
次に、段階的な電子化移行を進めていくことをお勧めします。
現状の帳簿保存方法の棚卸しを行い、電子取引データの保存方法を確立し、必要に応じて紙書類のスキャン体制を整え、クラウド会計・経費精算システムの導入を検討し、最終的には社内規程の整備と従業員教育を実施するというステップが効果的です。
